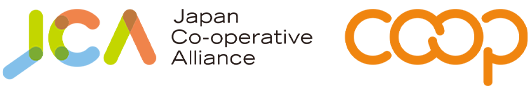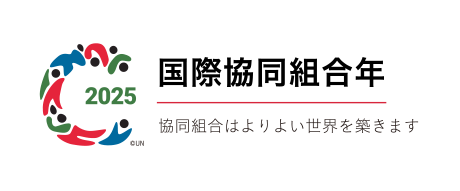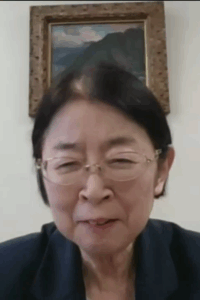- 2025国際協同組合年トップ
- “協同”がよりよい世界を築く~連続シンポジウム・座談会
第4回「SDGsと協同組合」開催報告
“協同”がよりよい世界を築く~連続シンポジウム・座談会
第4回「SDGsと協同組合」開催報告
7月5日(土)、IYC2025全国実行委員会は、東京国際フォーラム・ホールD1にて、「“協同”がよりよい世界を築く~連続シンポジウム・座談会」の第4回「SDGsと協同組合」を、同日開催の「見て、聞いて、体験 協同組合フェスティバル」のもとで開催しました。
第4回目となるシンポジウムは、二部構成での開催となり、第一部は「SDGsと協同組合~実践状況、達成への課題と期待」、第二部は「持続可能な暮らしのために、先人から学び、未来へつなぐ~協同組合の父 賀川豊彦とSDGs~」をテーマに進められました。
第一部は、①SDGsをめぐる状況を共有し、②SDGsジャパン関係者、市民組織、NPOなどの方々に協同組合の実践状況をご理解いただく機会とし、③ディスカッションを通じて協同組合によるSDGsへの貢献についての評価と今後の課題を明らかにする、ことを目的とするもので、会場62名、オンライン53名の計115名が参加し、211名の方からオンデマンド視聴の申し込みがありました。
詳細はこちら
冒頭、IYC2025全国実行委員会幹事長・比嘉政浩の開会挨拶・趣旨説明に続き、一般社団法人SDGs市民社会ネットワークの新田英理子理事・事務局長をコーディネーターに、慶應義塾大学大学院・政策メディア学部修士の落合航一郎様、一般社団法人SDGs市民社会ネットワークの大橋正明共同代表理事・恵泉女学園大学名誉教授、社会福祉法人全国社会福祉協議会の村木厚子会長(オンライン参加)、一般社団法人日本協同組合連携機構の比嘉政浩代表理事専務からのプレゼンテーションとパネルディスカッションが行われました。《プレゼンテーション》
- 「SDGsの現状、学生から協同組合への期待」 慶應義塾大学大学院・政策メディア学部修士 落合航一郎様
SDGsに関心を持ったきっかけや、世界・日本における達成状況について報告、特に森林破壊による生物への影響や、SDSN(持続可能な開発ソリューション・ネットワーク)の最新レポートに基づく評価に触れ、日本の課題を示しました。また、情報の正しい理解と行動の重要性を強調し、ESD(持続可能な開発のための教育)に関する自身の研究についても紹介しました。
- 「市民社会組織のSDGs、グローバル視点から協同組合への期待」 一般社団法人SDGs市民社会ネットワーク共同代表理事・恵泉女学園大学名誉教授 大橋正明様
SDGsの進捗が危機的状況にあるとし、市民社会の声と行動の重要性を強調しました。また、SDGsには法的拘束力がないため、市民による監視と政策提言が不可欠であると訴えました。協同組合の強さとSDGsの進展には明確な相関は確認できないものの、共に持続可能な社会を目指すパートナーとして連携の可能性についての示唆がありました。
- 「日本の社会福祉の現状と協同組合への期待」 社会福祉法人全国社会福祉協議会会長 村木厚子様
協同組合や市民活動との関わりから得た経験をもとに、SDGsの「誰一人取り残さない」の意味を理解し、社会課題解決には官民連携と市民の主体的関与が不可欠と述べました。日本の急速な少子高齢化や財政難を背景に、制度だけでは救えない人々を支えるため、地域共生社会の構築や「依存し合える自立」について提起しました。
- 「協同組合のSDGsーVNRからー」 一般社団法人日本協同組合連携機構代表理事専務 比嘉政浩
日本の協同組合が、組合員のニーズに応える民主的な事業体として、持続可能な社会の実現に貢献してきており、SDGsとの親和性が高く、組合員の関心も強いことがJCAの調査で判明したと報告しました。成功事例として移動販売やリサイクル事業が紹介され、志・ビジネスモデル・組合員の参加が鍵と指摘しました。
登壇者によるプレゼンテーションに続き、会場参加の日本生活協同組合連合会サステナビリティ推進グループの新良貴泰夫様より、「生協の2030環境・サステナビリティ政策」、「10の行動指針」や「2030年目標」(数値目標)をはじめとする生協のSDGsの取り組みが紹介されました。
《パネルディスカッション》
登壇者から、社会課題を身近な問題と感じるためには、当事者の声を直接聞くことや、個人の「好きなこと」と社会課題とを結びつけることが有効だと指摘がありました。また、協同組合の持つ学習の文化と他者との連携の重要性が強調され、異なる立場の人々と協力することが課題解決において不可欠であるとされました。さらに、世界の状況に対して日本の活動も胸を張って発信すべきだとの意見や、SDGs実現には一人ひとりの態度や協調性が鍵であるという発言がありました。最後に、コーディネーターを務めたの新田英理子理事・事務局長から「「一致できる点で連携する」ことの大切さと、課題を起点とした行動の推進」が呼びかけられました。
第二部は、①「協同組合の父」賀川豊彦が残した現在のSDGs実践につながる功績について振り返り、②賀川豊彦が理想と考え、SDGs達成度が高く協同組合が市民社会に根付いている北欧社会について学び、③日本の協同組合のSDGsの取組みと課題を考える、ことを目的とするもので、会場71名、オンライン59名の計130名が参加し、217名の方からオンデマンド視聴の申し込みがありました。
詳細はこちら
冒頭、IYC2025全国実行委員会事務局長・伊藤治郎の開会挨拶・趣旨説明に続き、一般社団法人SDGs市民社会ネットワークの星野智子理事をコーディネーターに、公益財団法人賀川事業団雲柱社・賀川豊彦記念松沢資料館の石部公男理事長・館長、大阪大学大学院人間科学研究科の斉藤弥生教授、生活クラブ事業連合生活協同組合連合会の伊藤由理子顧問からのプレゼンテーションとパネルディスカッションが行われました。
《プレゼンテーション》
- 「SDGs先駆者としての賀川豊彦について」 公益財団法人賀川事業団雲柱社理事長・賀川豊彦記念松沢資料館館長 石部公男様
明治末期の神戸の貧民街で貧困や飢餓に苦しむ生活困窮者への救済活動、助け合い精神のもとSDGsを体現する協同組合の推進、子どもの権利の尊重のための幼稚園・保育園の設立、など、加川豊彦が2015年に国連が採択したSDGsの先駆けとなる実践に取り組んでいたことが報告されました。
- 「北欧福祉社会と協同組合について」 大阪大学大学院人間科学研究科教授 斉藤弥生様
格差の小さい社会を実現しているスウェーデン、デンマーク(北欧)の福祉社会の特徴、賀川豊彦が戦間期の北欧を見て協同組合事業のもと隣人同士が協力する「共助のもと、自立して生活する人々」の姿に影響を受けたことが報告されました。
- 「生活クラブにおける「ローカルSDGsの取組み」とデンマークからの学びについて 生活クラブ事業連合生活協同組合連合会顧問 伊藤由理子様
生活クラブの関係者が「世界一幸福な国」といわれるデンマークを視察、全ての人が平等に権利と義務を有する全員参加型の福祉社会の現場、子ども(子育て)と高齢者(介護)は国が税金で支え大人は男女ともに働き社会・生活を支える福祉国家、協同組合型での風車事業やコレクティブハウス事業の運営、などに学び、地域の市民の協同によるつながりでFEC(食・エネルギー・ケア)自給を目指す生活クラブのローカルSDGsの実践が報告されました。
- 「賀川豊彦と北欧について」公益財団法人賀川事業団雲柱社理事長・賀川豊彦記念松沢資料館館長 石部公男様
デンマーク訪問で感銘を受けたホルケ・ホイスコーレ(国民高等学校)をモデルに農民福音学校を開設したのをはじめ、賀川豊彦が貧困層の救済、社会福祉の充実、協同組合の発展に北欧モデルを積極的に導入したこと、北欧発の福祉国家や協同組合運動の理念がその後の賀川豊彦の活動や思想の中核になっていること、が報告されました。
《パネルディスカッション》
登壇者から、①賀川豊彦が協同組合に求めた原点への回帰、②地域課題の解決に向けた生産者・消費者の連携構築、③北欧にはない日本の協同組合の特長の確認と発信や学び合い、④求められる全員参加協同組合型社会に向けた協同組合陣営としての連帯強化、⑤自由で自立した豊かな社会には慈善ではないつながり助け合う協同組合が求められることの強い発信、の重要性など、多岐にわたるコメントが出されました。
会場参加者からは、「自然災害と協同組合の課題の関係」についての質問も出され、原点にある助け合いの考え方や意識の広範かつ多くの人による共有・徹底、地域の助け合いを超えた地域間・協同組合間の助け合い、などの必要性についてのコメントもありました。
最後に、コーディネーターを務めた星野智子理事による、SDGsの先駆的実践者である賀川豊彦を強く発信し、協同組合の財産として伝えつつ、SDGs達成に向け協同組合が学び合い、取り組みを進化・強化させていくことが求められる、とのとりまとめでシンポジウムは終了しました。
 石部公男様 |
 斉藤弥生様 |
 伊藤由理子様 |
 星野智子様 |