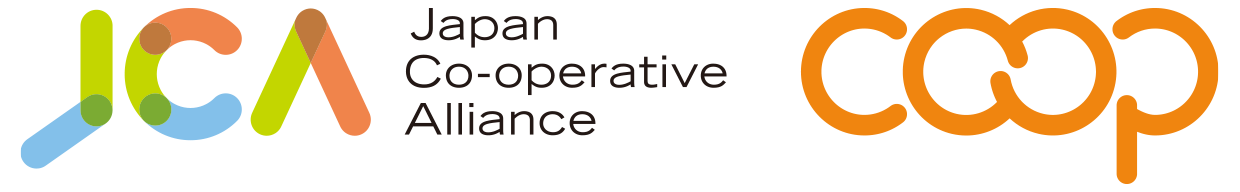国連事務総長報告「社会開発における協同組合」が 日本の取り組みを紹介
国連総会に対し2年に1回提出される国連事務総長報告「社会開発における協同組合(Cooperatives in social development)」の2025年度版(A/80/168)が、2025年7月15日に発表されました。
同報告は、本年11月に開催予定の第2回世界社会開発サミットを見据え、持続可能な開発目標(SDGs)の達成や、1995年の世界社会開発サミットがその成果として示したもの(貧困撲滅、完全雇用、社会統合など。「コペンハーゲン宣言」にまとめられている)の達成に向けた取り組みの進捗の遅れを指摘しました(「Ⅱ.コペンハーゲン宣言の達成におけるギャップ」)。
そのうえで、SDGsやコペンハーゲン宣言の達成に向けた協同組合の役割を評価し、「貧困の撲滅」「ディーセント・ワーク」「社会的結束と信頼の再構築」の各分野における世界各地の協同組合の取り組みを紹介しています(「Ⅲ.協同組合のやり方」)。さらに、「Ⅳ.2025年国際協同組合年」で、世界各地での国際協同組合年(IYC)の取り組みを紹介し、最後に、協同組合を支援する法制度や政策を各国政府に提言しています。
日本の取り組みとして、今年5月に国会で採択された「国際協同組合年にあたり協同組合の振興を図る決議」、2月19日に開催されたIYC2025キックオフイベントが、アジア太平洋地域におけるIYCの取り組みとして紹介されています(第51~52段落)。また、協同組合による高齢者支援の事例として、日本の生活クラブ連合会の取り組みが記載されています(第39段落)。
■国連事務総長報告の要旨(報告冒頭の「要旨」を抜粋)
本報告は、総会決議78/175【2023年12月の国連決議A/RES/78/175。IYCを宣言した決議でもある-JCA注】に基づき提出されるものであり、協同組合が持続可能な開発目標(SDGs)及び社会開発に関する世界サミットの成果を達成するために加盟国を支援する潜在能力を最大限に発揮できるよう支援する主要な政策と行動を概説するものである。本報告は、協同組合が民主的ガバナンスの強化、組合員教育への投資、影響力拡大のためのパートナーシップ拡大に注力する必要性を強調する。2025年11月に開催予定の第二回世界社会開発サミットを見据え、協同組合がディーセント・ワークの創出と社会的包摂の推進を通じて貧困撲滅に果たす役割を分析する。また、現在進行中の「国際協同組合年(2025年)」を記念して実施されている活動のハイライトを紹介し、持続可能な成長と協同組合の発展を支援するために加盟国が検討すべき一連の提言で締めくくっている。これには、協同組合法の改正、協同組合を国家的な開発計画への組み込み、能力強化のための対象を絞った財政支援の提供、協同組合の影響を追跡し、その研修、リーダーシップ育成、市場アクセスを支援するための国際機関との協力などが含まれる。
■日本でのIYCの取り組みに関連する記述(「Ⅳ.2025年国際協同組合年」>「アジア太平洋地域における国際協同組合年」より抜粋)
50.アジア太平洋地域は、協同組合のアイデンティティを強化し、一般の認識を広め、目標達成に向けた多様なステークホルダー間の連携を構築する機会として、国際協同組合年を積極的に活用してきた。国際協同組合連盟アジア太平洋地域(ICA-AP)と29カ国にまたがる加盟組織は、国際協同組合年以降、国家レベル、サブ地域レベル、地域レベルの取り組みに積極的に関与してきた。国際協同組合年は、公正で包摂的かつ持続可能な世界を構築する協同組合の変革力を示す絶好の機会と宣言されている。
51.この機会は日本の国会においても認識されており、衆議院と参議院は協同組合運動を支援する決議を可決した。この決議では、協同組合が目標の達成と社会経済的進歩の促進において果たす役割が強調されている。政府に対し、とりわけ協同組合を持続可能な地域社会の構築における強力な主体として位置付けるよう求めている。
52.国際協同組合年の地域キックオフイベントは、2025年2月20日に開催された。このイベントは、国際協同組合同盟アジア太平洋地域、日本の2025国際協同組合年全国実行委員会、およびILO駐日事務所が共催した。協同組合のリーダー、組合員、政府代表、若者参加者など700名(対面250名、オンライン450名)が集まり、持続可能な開発における協同組合の役割を称え、強化した。イランやマレーシアなどの国が国際年における活動計画を発表した。日本の茨城県と島根県も活動計画を発表した。全国大学生活協同組合連合会やICAアジア太平洋青年協同委員会などの報告者は、協同組合運動に若いリーダーを統合する必要性について議論した。
■日本の協同組合の高齢者支援に関連する記述(「Ⅲ.協同組合のやり方」>「C. 社会的な結合と信頼を再構築する」>「アジア太平洋地域において高齢者を支援する協同組合」より抜粋>
38.高齢者組織は、アジア全域に存在するコミュニティに根ざした組織であり、高齢者の福祉と社会的包摂の向上を目的としている。通常、高齢者自身によって結成・運営されるこれらの組織は多機能性を持ち、医療へのアクセス改善や健康的な高齢化促進のため、家庭訪問や健康教育セッションなどの活動を行っている。また、孤立を少なくするため、マイクロクレジットへのアクセスや相互支援ネットワークの提供も行っている。高齢者組織は国によって名称が異なる。ある包括的な研究は、東アジア・東南アジアにおける高齢者組織を調査し、健康・経済的安定・社会調和の促進におけるその役割を強調した。その研究によれば、成功している高齢者組織にはしばしば、強力なコミュニティからの支援、有能なリーダーシップ、地域のニーズに合わせた活動が共通して見られた。
39.日本では、生活クラブ連合会が、地域に根差した福祉サービスの一環として、高齢者を支援する特別プログラムを実施している。このプログラムには、介護サービス、訪問サービス、高齢者の雇用機会が含まれる。生活クラブ連合会は、高齢者が地域社会で活動的であり続け、つながりを持ち、支えられるよう支援する、人を中心とした福祉システムの構築に取り組んでいる。
【関連リンク】